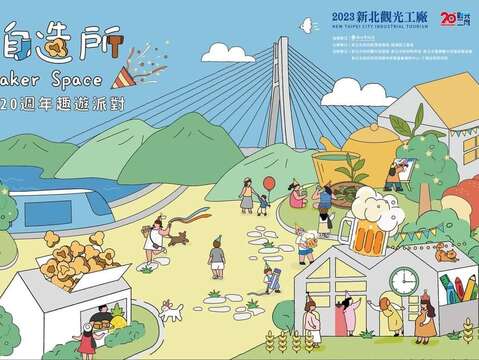「入れっ!」、「行けっ!」、 野柳神明浄港文化祭
人気 3789
数十年後、福建省から来た船が野柳の海に座礁、沈没しました。この悲劇の後、保安宮に祀られた開漳聖王が降臨し、漁師に対して犠牲者の遺体が港に入らないよう物を捧げて祈り、清めるように命じました。さらに開漳聖王は再び降臨して元宵節の際は自ら見回ることを伝えました。野柳の住民は神様の命令をに従って、若くて力のある信徒が正月15日に神輿を担いで冷たい海に飛び込み、港内の悪霊を退治しました。これが野柳神明浄港の起源と言われています。
「水裡来、火裡去」(水から来て、火を渡る)
野柳神明浄港は百年以上の歴史を有する、元宵節に北海岸で行われる独自の祭典です。平渓天燈節、塩水蜂炮と共に台湾の民族文化の無形財産です。野柳神明浄港では「浄海巡洋」、「漁獲満艙」、「神明浄港」、「神明過火」の4つの儀式が行われ、参加した信徒は必ず神輿を担いで水中に飛び込み、岸に上がった後はたき火を渡ることが必要です。これが「水裡来、火裡去」(水から来て、火を超える)の意味であり、萬里区で最も独得な文化的祭典です。
神明浄港は野柳地区で開催される毎年恒例の行事であり、野柳の住民と漁師全体が共同で資金や人材を出し合って共に盛り上げ、地元の人の力を結集する重要な祭典です。 神明浄港は早朝から賑わいを見せ、信徒たち、主祭が次々と保安宮へ入って祝福の儀式を行います。寺院前は野柳小学校の獅子舞団、北管楽社、神将の素晴らしいパフォーマンスに目を離す暇がなく、シャッターの音があちこちから聞こえて鳴り止みません。
寺院側が8台の神輿を保安宮前まで担ぎ、神像を手入れした後、爆竹を神輿にかけて、勇士が爆竹に火をつけた神輿を担いで前へ進むと爆竹の音が響き渡り、雨降る空を超えて天まで届きます。
浄海巡洋
皆の祝福を受けた曳船が出港し、浄海巡洋が始まります。漁港内には10艘以上の漁船は爆竹の音が響き渡る中、曳舟を追いかけて野柳漁港を出港します。一時間弱におよぶ浄海巡洋の儀式では全ての漁船が野柳漁港を三週して豊漁と出航後の安全を祈願します。
漁獲満艘
浄海巡洋後、漁船は保安宮前に戻り、船艘を開いて沢山積まれた魚をトラックに積み上げますが、これは今年出航の漁が豊漁であることを表しています。続いて市長主催のチャリティー水産物オークションが始まり、競りの場面の熱気は圧巻です。
神明浄港
「入れっ!」、「行けっ!」と皆が大声で叫ぶ中、注目の的は保安宮前で開始される神明浄港です。野柳の勇士たちは開漳聖王、媽祖、周倉将軍、土地公など8台の神輿を担ぎ、見学者の熱の込もった歓声の中、冷たい風が吹く中漁港へ飛び込むことで、百年前の開漳聖王が降臨して港を見回る情景を再現しました。これによって野柳漁港にはびこる悪霊を退治し、豊漁と人々の安全を祈願します。
神明浄港もまた、時代の変遷と共に一般の人々へ開放されるようになり、一緒に海へ飛び込み、飛び込みの大会も開催するようになりました。神輿が港に入ると100名が海に飛び込んで祭りを盛り上げます。2024年は辰年であることから、多くの人が辰年にちなんだ龍が描かれた衣装をまとい、辰年の到来を祝うと共に一年が平和であることを願いました。
神明過火
神輿を担ぐ勇士たちは港に入った後、神輿を担いだまま野柳港を泳ぎ、岸に上がった後は神の示す通り火を飛び越えることが必要です。「行けっ!」、「進めっ!」と大きな声が再び野柳に聞こえ、勇士たちは神輿を担いだまま、米と塩を撒いたたき火を裸足で歩くことで体の邪気を取り払い、3周すると「水裡来、火裡去」の儀式が完成します。
北管楽社の先導によって、あまたの神々が漁村を包み込んで、野柳を庇護します。神明浄港文化祭は百年前に海に漂流した神秘的な無人船を起源とし、船の中の開漳聖王は野柳の漁師によって岸へ迎えらえた後、船が座礁した際に降臨して港を見回り、野柳漁港の平和を守ってきました。野柳の住民はこの心意を現代まで受け継がれています。神明浄港は元宵節の行事だけではなく、野柳住民の間に世代を超えた記憶として共有されています。